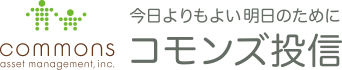<対談>統合報告書2024の行間を読み解く
丸紅株式会社IR・SR部 部長代理 吉田拓郎氏
丸紅株式会社人事部 企画課 北越涼也氏
聞き手:コモンズ投信運用部シニアアナリスト 上野武昭

上野 私たちアナリストが統合報告書を読む時、4つの観点を重視しています。①企業の価値観として何を大事にしているのか、②トップメッセージでは、歴史観に立って経営を行っているか、先を見ているか、人を大事にしているか、③事業の強みがどこにあるのか、④社員の方々の気持ち、です。社員の方々の気持ちとは、トップが社員のモチベーションを上げるための仕組みをどう作っているのか、それが社員に浸透しているのか、それらの結果として一丸になって前に進む気持ちが醸成された組織になっているのか、ということです。
まず、丸紅グループの価値観についてですが、2018年にロゴマークを変更されています。その理由から教えて下さい。
 吉田 2018年6月に、私たちがグループ一丸となって目指す在り姿として、「グローバル・クロスバリュー・プラットフォーム」を定義しました。2018年は創業160年という節目の年でもあったのですが、この変化のスピードが速い時代に、総合商社の役割、位置づけ、存在意義がステークホルダーに伝わりにくくなっているのではないかという想いがあり、改めて定義することになりました。
吉田 2018年6月に、私たちがグループ一丸となって目指す在り姿として、「グローバル・クロスバリュー・プラットフォーム」を定義しました。2018年は創業160年という節目の年でもあったのですが、この変化のスピードが速い時代に、総合商社の役割、位置づけ、存在意義がステークホルダーに伝わりにくくなっているのではないかという想いがあり、改めて定義することになりました。
統合報告書の2ページ目、価値観のところに掲げている赤い丸は、そのグローバル・クロスバリュー・プラットフォームを示しています。商社は、ともすればさまざまな事業体の寄せ集め的なイメージで見られがちですが、我々の本当の機能はプラットフォームであると思っており、そのプラットフォームのうえでグループの強み、社内外の地位、人の夢や志を掛け合わせて、世の中に新しい価値やモノ・サービスを提供する。そこを目指したいという想いがこの丸には込められています。
上野 確かに商社というと、エネルギーや食品、素材、航空・宇宙、インフラなど多岐にわたっていて、ともすれば縦割り組織になりがちですが、それをすべて融合させたうえで「丸」なのですね。
吉田 縦割りを突き破って丸になる、というイメージを想起させられればと思っています。近頃は変化のスピードが速いだけでなく、社会課題も非常に複雑化しており、その解決にあたっては、縦割り組織では対応が難しくなっています。縦横無尽に壁を破っていかなければ、生き残れなくなる恐れがあります。その危機感は強いですね。
上野 柿木社長のCEOメッセージで気になったのが、「当社は以前、利益成長を実現しては大きな減損を出して振り出しに戻るというような、業績のボラティリティが非常に高い時期がありました。株主の皆様からも丸紅は少し『荒々しい』という印象を持たれていたと思います。このような苦い経験から学び、2019年度の減損で大きな膿を出し切り、投資規律を強化したことで、現在の強固な収益基盤の確立に繋がりました。」ということですが、具体的にどういうことで、それをどう解決しようとしているのですか。
吉田 投資をする場合、社内の稟議プロセスを通じて案件を上げ、推進していきますが、過去には実現可能性が高いとは言えないシナジーに期待してプロジェクトを走らせてしまうこともありました。つまり案件そのものの収益性よりも、他の分野に波及すると思われるシナジーを織り込んだ事業計画を立てて推進したものの、実はなかなか地に足のついたシナジーが生まれて来ず、計画通りにいかない投資案件や減損を出してしまうということもあったのです。
そこで今は、シナジーを一旦横に置いておき、案件そのものがしっかり収益を生み出せるものなのかという点を吟味したうえで、投資の可否を判断するようにしています。それが業績の安定にもつながっていると考えています。
 上野 人財戦略のところで、柿木社長がグループ社員の方々と直接質疑応答を行う「Opinion Box」ですが、単純に凄いことだなと思います。どうすれば、社員数が多い中で、多くの数の質疑応答に対応できるのでしょうか。
上野 人財戦略のところで、柿木社長がグループ社員の方々と直接質疑応答を行う「Opinion Box」ですが、単純に凄いことだなと思います。どうすれば、社員数が多い中で、多くの数の質疑応答に対応できるのでしょうか。
吉田 恐らく累計で、これまで1500件程度のグループ社員からの質疑に答えていると思うのですが、柿木は土日も使って、回答を発信しています。柿木としては、グループ社員も大事なステークホルダーだと認識しており、その対話を重視しています。
上野 丸紅株式会社は米国で非常に強い競争力を維持しています。当期利益の約3割を米国で稼ぐほどですが、なぜここまで米国のビジネスに強みを発揮できるようになったのでしょうか。
吉田 初めて米国の地を踏んだのは、1951年にニューヨーク現地法人を設立した時です。以来、貿易を中心にして米国ビジネスを大きくしていき、いわゆるヒト、モノ、カネといった経営資本を蓄積していきました。
そして、1970年代からはそういったトレードに加えて事業投資も積極的に行うようになり、成功と失敗の経験を積み上げ、米国におけるノウハウ・ネットワークを拡大してきました。やはりアメリカ進出の70年間に及ぶ歴史のなかで地道に積み上げてきたものが大きいということだと思います。
それらは主に各事業本部で積み上げてきましたので、今後は事業の掛け合わせにも更に取り組むことでさまざまなシナジーを生み、企業価値の向上につなげていきたいと考えています。
上野 社員と企業の信頼関係の深さを数値化したものに、エンゲージメント指数があります。御社の場合、2024年3月期の同指数が62.4ですが、この数字が意味するところと、社員持株会の加入率が94.5%という驚異的な高さが何を物語っているのか、教えて下さい。
 北越 当社においてエンゲージメントとは、「個人と組織が一体となり、双方の成長に貢献し合う関係」と考えています。当社のエンゲージメントスコアは62.4(偏差値)となりますが、(株)リンクアンドモチベーションが2023年に従業員エンゲージメント調査を実施した企業の中から、エンゲージメントスコアの高い10社を表彰する「ベストモチベーションカンパニーアワード2024」の大手企業部門で2位にランキングされるなど高い水準にあると考えています。
北越 当社においてエンゲージメントとは、「個人と組織が一体となり、双方の成長に貢献し合う関係」と考えています。当社のエンゲージメントスコアは62.4(偏差値)となりますが、(株)リンクアンドモチベーションが2023年に従業員エンゲージメント調査を実施した企業の中から、エンゲージメントスコアの高い10社を表彰する「ベストモチベーションカンパニーアワード2024」の大手企業部門で2位にランキングされるなど高い水準にあると考えています。
エンゲージメントスコアが上昇した部署にヒアリングをすると、上司と部下のコミュニケーションの活性化、メンバー間の連携強化、自律的な行動や闊達な議論の増加など、個人と組織の信頼関係が高まり、新たな価値創造につながるプラスの効果が出ていることが明らかになっています。
全社のスコアを上げることも重要ではありますが、それ以上に、低スコアの組織がどの程度あり、それをどう改善するかに重点を置いています。スコアの改善を希望する組織に対しては、「組織改善プログラム」を提供することで、より多くの組織とメンバーの信頼関係が強固な状態になることを目指しています。
また、当社の持株会制度については、より多くの社員が持株会に加入し、保有株式が増えることで、社員の資産形成に寄与するとともに、社員一人ひとりの経営参画意識や、企業価値向上への一体感を高めたいとの考えで、特別奨励金の支給を行っています。加えて積極的な社内周知を継続した結果、2021 年度の加入率は50.1%だったところ、2022 年度は86.0%、2023 年度には94.5%にまで上昇しています。
上野 本日はありがとうございました。
前のページ:丸紅株式会社との対話~統合報告書2024に込めた想い~
本セミナーのアーカイブ動画はこちら