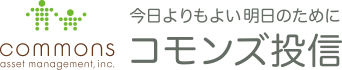株式会社メディアドゥは、漫画を中心にして日本の電子出版物を取り次ぐ流通ビジネスを展開している会社です。
紙の本がデータ化されることによって、低迷続く出版業界は新たな活路を見いだせるのでしょうか。電子書籍の市場はどこまで伸びるのでしょうか。
執行役員でChief Strategy Officer経営企画室長の苅田明史氏に、コモンズ投信代表取締役社長の伊井哲朗と、同社運用部シニア・アナリストの上野武昭が話を伺いました(2020年10月21日にオンラインイベントを開催。アーカイブ動画はこちら)。
電子書籍市場の可能性
上野 著作物から派生するさまざまなコンテンツは、日本が世界に誇れる成長産業だと思います。
御社は過去5、6年で売上が10倍に伸びましたが、それを牽引しているのが電子書籍の取次業務です。このビジネス領域はいつまで伸びると考えていますか。
苅田さま インプレス総合研究所のレポートによると、電子書籍市場は2024年に5600億円の市場規模になると予測しています。
ちなみに2019年に比べると1.5倍です。この数年、毎年大幅な上方修正がなされていることもあり、我々としてはそれ以上の成長を期待したいところです。
このところの電子書籍市場は漫画を中心に拡大してきましたが、デジタルではなく紙のマーケット自体がようやく下げ止まってきました。それに上乗せされる形で、漫画がデジタル化によって市場規模を大きく伸ばしてきました。
デジタル化によって、漫画がスマホゲームで時間を潰していた人たちの可処分時間を取り込んだ形です。
また小説などの文字物ですが、こちらの市場規模は日本の場合、海外に比べてかなり立ち遅れています。その分だけ伸びしろが大きいとも言えますので、もしここに火が付けば、電子書籍の市場規模は5600億円を超えて大きく成長する可能性もあると考えられます。
上野 それに加えて、「鬼滅の刃」のような大ヒットコンテンツがあれば、さらに市場規模が大きくなることも期待できるというわけですね。
苅田さま そうですね。漫画の場合、まだ大人に浸透していない作品が大人の間で人気化すると、いわゆる「大人買い」によって一気に売上が伸びます。
実際、電子漫画の上位20タイトルのうち、今、大ヒットしている鬼滅の刃は19タイトルを独占しました。
自分たちの指針として、統合報告書を発行
上野 統合報告書について伺いたいと思います。私たちアナリストにとって、統合報告書は非常に重要な資料で、企業調査をする時には、ほぼ全部に目を通します。
一般的な統合報告書のつくりは、冒頭が創業の歴史で以下、企業理念、経営トップの言葉、事業内容と続くわけですが、御社の統合報告書はメディアドゥの存在意義や企業理念にかなりのページを割いており、そこに社員が写真で大勢登場しています。
それが10ページくらい続いてようやくトップのコメントになるわけですが、このような構成にした理由は何なのでしょうか。
苅田さま 統合報告書の冒頭に存在意義や企業理念を持ってきたのは、それを社内外の方たちにご理解いただきたかったからです。

私たちはこの電子出版業界において卸しの立場ですが、卸しの存在意義は私たちだけが売上を伸ばすのではなく、業界全体を発展させなければ意味がありません。
電子書籍のマーケットは、出版社と電子書店が大きなプレイヤーです。出版社は面白いコンテンツをリリースすることによって、そして電子書店は出版社がつくったコンテンツをプロモーションしてユーザーに届けることで売上を伸ばします。
その中では出版社、電子書店、作家が、ユーザーである読者に対してプラスになる価値創造が必要になります。
私たちにとっての統合報告書は、こうした業界内における私たちの位置づけや経営の方針などについて、ステークホルダーはもとより、社内の理解促進にも役立てることによって、全体の方向性を統一させる意味もあります。
メディアドゥの社員の出自は実に多様です。
3年前に出版デジタル機構という、デジタルコンテンツ配信で業界トップの会社を買収しました。私がメディアドゥにジョインしたのも、自分が経営している会社をメディアドゥに売却したからです。
あるいは新卒も採用していますが、中途採用にも積極的です。そのためにさまざまな出自の社員がいます。
だからこそ、自分たちはどういう方向を見て進めば良いのかを指し示す指針として、統合報告書を活用している面もあります。
上野 本来、統合報告書はアニュアルレポートをはじめとして、企業がIR向けに作成している各種報告書をまとめて1冊にしたところからそう言われているのですが、御社の場合はさまざまな出自の社員に同じ方向を見てもらうためのツールという意味合いもあるのですね。
苅田さま それがひとつの目的です。それに加えて開示体制を強化するという意味もあります。
2年前まで、外国人投資家の持株比率は数%でしか無かったのですが、今年の8月時点では24%まで高まっています。
そのためESGやKPI、英文開示など取り組むべきことは他にもたくさんあるのですが、まず統合報告書を作成することによって、開示体制のなかで何が足りていないのかを見定めて、今後の改善点を探ろうと考えています。
上野 統合報告書にある藤田CEOのメッセージでは、ブロックチェーン技術の活用について触れられています。具体的に、どのようなプロダクトを考えていらっしゃるのですか。
苅田さま 具体的にどのようなプロダクトになるのかについては、これからリリースしていきますが、今、手掛けているブロックチェーンはコンソーシアム型で自社開発しているものです。
通常、ビットコインなどに用いられているブロックチェーン技術だと、1秒あたりのトランザクションは8回程度なのですが、私たちが現在開発しているブロックチェーンは、1秒あたり5000回のトランザクションを可能にしている、非常に処理速度の速いものになります。
ユーザーのIDとコンテンツのIDを保証するなど、ブロックチェーンを用いることによって実現する仕組みはさまざまです。
私たちは高い技術力を持っているので、それをデジタルコンテンツ業界にどんどん活かしていきたいと考えています。

コロナ禍での進化、業界全体を牽引する存在に
伊井 新型コロナウイルスのパンデミックを受けて、在宅勤務者が増えていると思います。現時点における社員の方々の働き方がどうなっているのか、その働き方によって、ブロックチェーンなどさまざまな技術開発に何か影響が生じないのかについて教えて下さい。
苅田さま 弊社では新型コロナウイルスの影響が顕在化してきた2020年1、2月あたりから働き方を変えて、徐々に在宅勤務を増やしていきました。部門にもよりますが、3月時点の出社率は50%程度で、緊急事態宣言が発令された4月時点では、98%程度が在宅勤務になりました。
ただ、リモートワークについては新型コロナウイルスとは関係なく、私たちとしては必要な勤務形態だと認識しており、今回のパンデミック騒動が起こる前から着手していました。
これからの時代、リモートワークが出来ないような企業は、エンジニアを採用する際の競争力で後れを取ってしまいますし、弊社の場合、営業も外回りで新規拓するよりも、すでにお付き合いいただいている出版社の方々とのウェブ会議を通じて、何を売り出すのか、どういうキャンペーンを企画するのかを打ち合わせるスタイルが主になるため、在宅勤務でもほとんど影響がありません。
緊急事態宣言が解除された今、徐々に出社する人は増えていますが、それでも以前に比べて出社率は低く、3割程度に抑えています。
通常業務は在宅で行う一方、顔を合わせることによって新しい発想が生まれるかも知れないような、クリエイティブな会議は出社して行うという、在宅と出社を組み合わせた勤務体系が、これからの私たちの主流になっていくと思います。
伊井 菅新政権のもと、国もようやくデジタル化に向けて本腰を入れてきました。そのなかで電子図書館の拡大や学校図書の電子化といった動きも出てくると思いますが、それについてはどのような見方をしていらっしゃいますか。
苅田さま 出版業界でもだいぶIT化は進みましたが、その波を享受できたのは大手出版社だけでした。
しかし、出版業界は中小のプレイヤーが非常に多いため、業界全体にIT化が広がらなかったのも事実です。私たちの存在価値は、出版業界におけるDX推進を支援することにあると認識していますが、それを実現するためには、世の中全体を支えるインフラのようなシステムを導入することによって、大手出版会社だけではなく、出版業界全体でDXを実現させることが必要であり、そこに私たちの技術力を用いて貢献していきたいと思います。
電子図書館については、高齢者が遠方の図書館まで行かずに済むことや、運営コストが安く済むという理由で導入するところが増えているものの、北米では95%の自治体が電子図書館を導入しているのに対し、日本はまだ数%に過ぎません。私たちは北米の電子図書館で9割のシェアを持っているオーバードライブ社の日本代理店なので、各自治体が電子図書館の導入を進めれば追い風になります。
伊井 電子図書館が普及した時、通常の図書館はどうなるのでしょうか。
苅田さま 利便性は電子の方が優れていますが、リアルの図書館は読みたい本を借りるだけの場ではなく、コミュニティです。しかも、今まで出会ったことのない本に出会えるチャンスの場でもあります。こうしたリアル図書館の存在意義は変わりません。
恐らく、電子図書館が完全にリアル図書館に置き換わるようなことにはならないでしょう。もちろんデジタル化したほうが良い部分もあるので、リアル図書館にデジタルの価値観を上乗せしたうえで、既存のリアル図書館のサービスを、より良いものに改善していくことになると思います。
伊井 デジタル化が進むことによって作家の著作権には何か変化が出てきますか。
苅田さま 著作権は最終的に作家に帰属します。これは紙媒体でもデジタル媒体でも変わりません。
ただ、著作権の拡大余地はデジタル媒体の方が大きいと思います。現在、海外ではオーディオブックの市場が2ケタの伸びで成長しており、電子書籍に次ぐ規模になってきています。
耳を使って「本を聞く」というのは、今までになかった、デジタル化によって生まれた新しい価値観です。
このようにDXが進むことによって、著作物が本以外の形式でも提供できるようになるので、著作権の幅が広がります。
伊井 競合相手をどう見ていますか。
苅田さま よく電子書店や出版社を競合他社と考えられがちなのですが、実は両者とも弊社にとって競合他社ではなくお客様であり、ともに出版業界を盛り上げていく同士のような存在であると認識しています。
私たちはあくまでも出版社と電子書店の間で、電子書籍の流通とDXを推進していく立場であり、業界全体の活性化がゴールであると考えています。
伊井 グローバル展開についてはどう考えていますか。特にグローバルな電子書店といえばアマゾンがまさに巨人として君臨していますが、どのような関係を構築していくのでしょうか。
苅田さま 4年前に米国のサンディエゴにメディアドゥインターナショナルを設立して、日本の漫画コンテンツを海外に提供しています。
また先日、米国で30年以上にわたり出版のIT化を進めてきたファイアーブランド・グループ2社の全株式を取得して子会社化することで基本合意しました。これによって北米における出版のDX成功事例を国内に導入するのと同時に、ファイアーブランド・グループの顧客基盤を活用して国際事業を拡大してまいります。
伊井 ありがとうございました。
2020年10月21日に開催したオンラインイベントのアーカイブ動画はこちらからご覧いただけます。