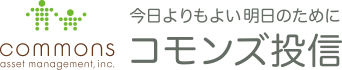コモンズ投信が株式会社小松製作所(以下「コマツ」)に投資したのは、2009 年 1 月に「コモ
ンズ 30 ファンド」の運用をスタートさせた時からです。以来、16 年超にわたって投資し続け
てきました。
コマツは 2021 年に創立 100 周年を迎え、2025 年度からは新中期経営計画「Driving valuewith ambition」において、「安全で生産性の高いクリーンな現場を実現するソリューションパートナー」という新しい企業像を打ち出し、新しい 100 年に向けて歩み出しています。
そのコマツが今後、どのような成長路線を考えているのか、目指す姿について、経営管理部 IR グループグループマネージャーの古賀智氏に話を伺いました。
<コマツの古賀様(スクリーン右側)>
私の自己紹介からさせていただきます。コマツに入社して 30 年目を迎えました。主に経理部門でキャリアを積んできています。
海外勤務も経験しました。ロシア、中国、チリに足掛け 13 年間駐在し、残りが日本での勤務です。経理財務部門の人が子会社に出向したり海外駐在する場合、それぞれの経理財務部門に行くことが多いのですが、私の場合はそれに加えてファイナンス事業、機械を買ってくれるお客様にリースなどを提供する、いわゆるお金を貸す仕事もしていました。またロシアに赴任した時は、コマツとしてロシアに初の生産工場を建てるプロジェクトに最初のメンバーとして従事し、まるで越冬隊員のようでした。現在の部署に来る前は、チリに赴任しており、鉱山開発事業の知見を深めました。これらの経験が、コマツの事業全般を把握し、投資家に情報を分かりやすくお伝えする、IR という仕事の役に立っています。
コマツの創業者である竹内明太郎は、戦後の日本復興を支えた政治家、吉田茂首相の実兄に当たります。加えて、日産自動車の創設メンバーや、早稲田大学理工学部の創設者でもあります。こうして様々な事業に関わるなか、石川県の小松市にある遊泉寺銅山の開発に着手し、その銅山で使う機械を修理するために設立されたのが、コマツの前身である小松鉄工所でした。
コマツの歴史を振り返ると、1990 年代までは国内事業が売上、利益の多くを占めていました。それが 2000 年を境に新興国のマーケットや、鉱山機械ビジネスが大きく伸びたことによって、売上、利益ともに大きく成長しました。
現在の会社の経営状況は、2025 年 3 月末の売上高が約 4 兆 1000 億円、営業利益が6,500 億円、従業員数が 6 万 6,000 人、子会社が 217 社で、売上の 90%が建設機械・車両部門からもたらされています。
主な製品は、コマツというとブルドーザー、ショベルカーのイメージが強いかと思いますが、近年、大きく伸びているのが鉱山機械で、2025 年 3 月期は鉱山機械の売上比率が建設機械を上回り、建設機械・車両部門の 50%以上になっています。鉱山機械が成長した理由は、鉱山ビジネスが好調であることに加え、鉱山機械の部品やサービスの割合が伸びているからです。
将来を見据えて今後 3 年間の中期経営計画を策定
今から 4 年前、100 周年を迎えた時、コマツが目指す会社の在り方をもう一度定義し直しました。
コマツの経営の基本は、「品質と信頼性を追及し、企業価値を最大化すること」と定められています。そして、ものづくりの会社なので、企業理念として「ものづくりと技術の革新で新たな価値を創り、人、社会、地球が共に栄える未来を切り拓く」と定義しました。
また、私たちの価値観として、「挑戦する」、「やり抜く」、「共に創る」、「誠実に取り組む」の 4 つをコマツの社員 1 人ひとりが、ずっと大切にし続けています。ちなみに、この 4 月に
社長兼 CEO に就任した今吉琢也は、この 4 つのうち「挑戦する」ことを重視したいと言っています。
今年、今吉新体制になってから、新中期経営計画を策定しました。将来を見据えてそこからバックキャストし、今後 3 年間の経営戦略を立てたもので、私たちのありたい姿として、
「安全で生産性の高いクリーンな現場を実現するソリューションパートナー」になることと再定義しました。
この中期経営計画を策定するにあたって、政治、経済、環境、技術という 4 つの外部環境について、中長期な変化の方向性を予測しました。
例えば、政治は自国中心主義が台頭していますし、経済では世界人口が増加する一方、
日本をはじめとする先進国の人口は減少傾向にあり、経済の重心がシフトしつつあります。さらに環境においてはカーボンニュートラル、技術に関してはグリーン化・デジタル化技術の開発が挙げられます。
こうした問題、課題に直面するなかで、我々の主力製品である鉱山機械や建設機械を、どのようにして世の中のトレンドにアジャストさせるべきなのかを考えたうえで、成長戦略について 3 つの柱を立てました。「イノベーションによる価値共創」、「成長性と収益性の追求」、「経営基盤の革新」がそれです。
成長戦略 3 本の柱の中身
「イノベーションによる価値創造」について申し上げると、脱炭素への流れは不可逆的です。鉱山機械、建設機械には様々なニーズがありますが、例えば鉱山機械の超大型ダンプには、ディーゼル、水素、フューエルセルなど複数のパワーソースで動かせるように開発を進めています。
あるいは、ディーゼルエンジンを用いた車両に、トロリーといって電車の架線のようなもの
をつけ、2 つの動力源で動かすことによって、トータルで排出ガスを削減する試みも行って
います。
ところで、排出ガスの削減となると、一般的にはバッテリー搭載モデルを思い浮かべるところですが、これがなかなか普及しません。私どもも、2023 年から 20 トンクラスの油圧ショベルをはじめ、5 モデルのバッテリータイプの油圧ショベルを販売していますが、需要は非常に小さい状況です。
私たちも、動力源としてバッテリーがカーボンニュートラル達成のひとつの手段になると考えていますが、現状では、鉱山機械や建設機械において、バッテリーモデルのマーケットが大きな割合を占めるとは考えていません。というのも、ショベルカーやダンプカーなど、力を一気に出さなければならない車両の動力源は、まだバッテリーでは技術的に限界があります。
こうした技術的問題に加え、そもそも建設や鉱山の現場では電源確保と充電に難があり、現状ほとんど普及していません。コマツでは、カーボンニュートラルのロードマップを示していますが、それによると機械から排出されるガスを削減するためにバッテリーで賄う部分は将来においてもあまり大きくないと見ています。さまざまなパワーソースを研究し、バッテリー以外の方法で排出ガスを削減できるよう努力しています。
次に、成長性と収益性の追求です。様々なソリューションを展開するためには、会社を成長させ、しっかり利益を上げなければなりません。その柱のひとつが鉱山ビジネスです。世界的に鉱山ビジネスが活況を呈していることに加え、資源価格の上昇によって、かつてはコスト高で採掘できなかったような場所での鉱山開発も可能になってきました。これから私どもが鉱山機械を入れていくパキスタンもそのひとつです。現在、マイニング伝統国からもたらされる売上が 9 割を占めていますが、今後はそれ以外の国にある鉱山開発の現場に鉱山機械を入れて、収益を増やしていく方針です。
また、一般建機においては人手不足、熟練オペレーター不足という問題が、特に先進国では深刻化しています。そこで昨年 12 月から、PC200i という建設機械を日本に導入しました。これは、3D マシンガイダンスといって、図面を機械が読み取り、その通りに機械を動かす機能を持った建設機械です。機械がガイドする通りに操作すれば、熟練オペレーターと同じように機械を動かせますし、更に高い機能にアップグレードすればより自動に近い動きを機械ができるようになります。
しかも、ソフトウェア・ディファインド・ビークルといって、お客様が求める機能に応じてソフトウェアをアップデートすれば、さまざまな機能に合わせて動かすこともできます。
最後に、「経営基盤の革新」ですが、コマツは今まで質実剛健、社会の縁の下の力持ちというイメージを売ってきたのですが、今後、グローバルで戦おうとした場合、ブランド認知力が重要になってきます。そこがコマツの弱さでもあったので、それを強化するため、大阪万博やキッザニア東京への出展に加え、2024 年シーズンからウィリアムズ・レーシングと複数年契約を結ぶなど、様々なところでブランドイメージを打ち出しています。
SLQDC で考え行動する
そして最後にサスティナビリティ基本方針ですが、これは「人と共に」、「社会と共に」、「地球と共に」を挙げています。
いささか範囲が広いので、コマツの特徴とひとつだけ出しますが、様々な事業を行ううえで大事にしているのが、SLQDC という考え方です。
S は Safety(安全)、L は Law(法律)、Q は Quality(品質)、D は Delivery(配送)、C はCost(コスト)です。何か判断に迷うことがあったら、この判断基準で考えるということで、その共通認識を持たせるような社員教育を行っています。
それと同時に、社会課題の解決を唱えていますが、それを皆さんにどのような形で示せば良いのか。これはなかなか迷うところではありますが、ひとつのやり方として、今後は非財務情報の開示の充実を図って、その可視化をしていきたいと思います。
例えば、私どもの無人ダンプトラックは、2025 年 3 月末時点において世界で 862 台導入・稼働していますが、今まで事故によって人が亡くなったケースは 1 件もありません。その社会的な価値をインパクト加重会計で計算すると、実に年間 3,600 億円のベネフィットを世界に与えています。財務諸表上の数字には表れませんが、こうした非財務情報を高めることによって、私たちの企業価値をもう一段、高められると考えています。

<コモンズ投信の金子・古川(スクリーン左)>
<鼎談>
コマツの現状とこれからの戦略を聞く
コマツ経営管理部 IR グループ グループマネージャー 古賀智氏
コモンズ投信アナリスト 古川輝之氏
コモンズ投信ポートフォリオマネージャー 金子敏行氏
サプライヤーや代理店と共に発展を目指す
古川 御社が常に業界のリーダーとして、一歩先んじることができる先見性や経営判断は、
何から生まれるものなのでしょうか。
古賀 経営者が常に一歩先を読もうとしていることは、中にいる社員の立場で見ても分か
ります。その一番の理由は、キャタピラーの存在ではないでしょうか。キャタピラーはグ
ローバルで最も強い競争相手ですが、真正面からぶつかっても跳ね除けられてしまい
ます。何しろ相手は米国という巨大マーケットを抱えていますから、物量ではなかなか
勝てません。したがって、私たちはキャタピラーとは違う軸を打ち出して勝負する必要
があります。違う軸とは、具体的には技術力の高さと先進性です。それを手に入れる
ためのひとつの手段としてこれまで M&A を積極的に行ってきました。
古川 2025 年 3 月期の連結決算は、過去最高益を更新しました。バランスの良い経営を
しているように見受けられます。
古賀 最高益を更新できたのは、長年の積み重ねの結果だと考えています。今、非常に
好調を維持している鉱山ビジネスは、かれこれ 1980 年代の後半から取り組んできたも
のですし、超大型ダンプについても、その技術は 1988 年に米国のドレッサーという会
社の株式の半分を取得した後、100%子会社にして技術を取得したからです。だいぶ
時間は経過しましたが、その時の取り組みが今になってようやく花開いたというのが、
現実だと思います。
古川 M&A のシナジー効果もさることながら、御社はステークホルダーと共に成長してい
こうという想いを強く感じます。それはなぜですか。
古賀 自動車業界に比べると鉱山機械・建設機械業界はニッチです。例えば、自動車の
生産台数は、全世界ベースで年間 1 億台あります。一方、鉱山機械・建設機械業界は
50 万台です。そうなるとサプライヤーやディストリビューター(代理店)も、自動車業界
に比べて基盤が強いわけではありません。例えば、トヨタ自動車の系列サプライヤー
であるデンソーやアイシンは、いずれも名だたる上場企業ですが、鉱山機械・建設機
械の系列サプライヤーにそこまでの経営規模を持つところは皆無ですし、ディストリビ
ューターも、例えば、自動車メーカーは各地域の財閥や大手企業と組んでいたりしま
すが、コマツにそこまでの代理店は存在しません。だから、皆で協力しないと成り立た
ないのです。すべてのステークホルダーが皆、幸せになるように、等しくベネフィットを
得られるようにすることが大事だと考えています。
古川 過去、不況でサプライヤーが苦境に陥った時、銀行に同行して一緒に追加融資を
お願いしたり、サプライヤーの設備を御社が一旦、買い上げた後にリースバックして、
一時的に資金繰りを助けたりしています。あるいは御社の経営会議に、サプライヤー
などの経営状況も議題に挙げるという話も耳にします。正直、驚きました。
古賀 サプライヤーは大事です。サプライヤーがするべき仕事は全面的に任せ、私たち
は、私たちでしかできない仕事に専念してお互いに協力する。その関係性をしっかり構
築しないと、コスト削減も品質向上も出来なくなってしまいます。
大規模鉱山ビジネスはキャタピラーとコマツの独壇場
古川 今後の成長戦略について 3 本の柱を立てられました。まずイノベーションですが、
それを進めていくうえで留意していくことは何でしょうか。
古賀 今後もキャタピラーには技術面で勝たなければならないので、そこは重視している
のですが、例えば、新興国になると、そこまでの先進技術はお客様にとって Too Much
だったりします。キャタピラーに勝つうえで、さまざまな先進技術の開発には注力しま
すが、そこまでの製品は必要ないとおっしゃるお客様が多いのも事実で、そのニーズ
にも合致する製品を出すことも大事です。とはいえ、いずれ新興国も人手不足に陥る
時が来るでしょうから、その時に即、対応できるようにするための準備は、今から行っ
ていく必要があると考えています。
古川 先進国を意識した場合、IT 技術の潮流はどこにあるのですか。
古賀 先進国で最大の課題は人口減少による人手不足であり、それが今、顕著に表れて
いるのが日本です。ですから、まずは日本で人手不足対応、熟練オペレーター不足対
応のためのビジネスモデルをつくりたいと考えていますが、国によっては自動化に対
する好き嫌いも含めた考え方や価値観の違いもあると思います。ただ、最終的に私た
ちはハイテク製品で勝負したいので、まずは自動化のニーズがあるであろう国や地域
のお客様に、自動建機の価値を分かっていただくための活動を展開する必要がありま
す。また、機械そのものを購入してもらうだけでなく、部品やアフターサービスなどのア
フターマーケットで収益を上げるのがコマツのビジネスモデルなので、そこも怠らない
ようにする必要があります。
古川 機械の販売や、その後の部品やサービスの販売は、キャタピラーという巨大な競合
相手だけでなく、価格面では中国メーカーとも競争していく必要があり、それはなかな
か熾烈だと思うのですが、御社としては、どのようにリソースを割いていくつもりですか。
古賀 確かに純粋な新車の販売価格の競争という点では、中国メーカーに敵いません。
ただ、正直なところ中国メーカーを利用しているお客様の中にも、ローエンドの製品だ
けでなく、ハイエンドの製品を求めているケースはありますし、新興国といえどもハイエ
ンドに比重が掛かっているところもあります。ですから、そこはマーケットの状況を把握
して、それに適した製品を提供することが大事だと思います。
正直なところ、中国ブランドと同じ戦略で戦っても仕方がないので、やはり最終的には
ハイエンドのお客様が納得して下さる信頼性、耐久性を担保したうえで、代理店のサ
ービス、ネットワーク、部品の供給も担保されている、といった点を評価して下さるお客
様を強化し、利益を確保していこうと考えています。
古川 今のところ、大規模鉱山などに中国系メーカーが参入する気配はありませんか。
古賀 大規模鉱山でこの手の動きはありません。なぜなら、彼らはライフサイクルコストと
いって、機械を購入し廃棄するまでのトータルコストを重視して、それに加え安全性を
重視します。その他、機械の生産性、部品の供給、壊れた時にすぐ治せるサービス体
制にあるのかどうか、といったことを総合的に判断するので、簡単に他メーカーが入れ
る余地のない世界です。One Stop で製品を提供できるフルラインメーカーはコマツとキ
ャタピラーだけであり、非常に参入障壁の高いビジネスです。
パキスタンの鉱山ビジネスは今後 40 年続く巨大プロジェクト
古川 成長性と収益性の追求でカギになると見られている、中央アジアや中東での戦略
を教えて下さい。
古賀 コマツ全体の売上のうち 18~19%が中南米で、その半部以上がチリの鉱山からも
たらされています。チリで採掘されている鉱物の大半が銅ですから、コマツの売上、利
益の大半はチリの銅からもたらされていると言っても過言ではありません。
なぜチリのビジネスが成功したのかというと、その地域にいち早く進出したからです。
強力な代理店ネットワークを構築し、すべてコマツに任せてくれという体制を築いたとこ
ろ、サービスがどんどん拡大し、利用率も高まりました。その代わり巨大なオペレーシ
ョンなので、コマツの従業員 6 万 6,000 人のうち、チリだけで 8,000 人から 9,000 人が
働いています。
今後、鉱山ビジネスを成功させるためには、直販、直サービスでお客様の満足度を高
める、チリのビジネスモデルが有効だと考えており、パキスタンでも同様に、直販、直
サービスの体制を整えます。今回プレリリースで発表されたものは機械の販売で 4.4
億ドルですが、部品販売やアフターサービスを含めると、さらに大規模になり、この鉱
山は今後 40 年間稼働すると言われており、今後のコマツのビジネスの更なる拡大も
見込めます。
古川 グローバルにビジネス展開をすると、どうしても政情不安などの政治リスクに直面
するかと思います。そこへの対処はどう考えていますか。
古賀 それは過去に何度もありました。例えば、1980 年台初頭にはイランの石油開発向
けが非常に多くありましたが、今はゼロです。世界のダイナミックな動きのなかでは、
政治的な要因がビジネスに影響することはあります。現状ではロシアがそれにあたり、
ピーク時に 2,000 億円弱あった売り上げは非常に小さくなっています。
でも、いろいろな地域の鉱山ビジネスに分散させて売上を立てておけば、2025 年 3 月
期のように過去最高益を更新することも起こり得ます。実のところ、ロシアは非常に利
益率の高い地域だったのですが、そこがダメになったとしても、ビジネスを分散させる
ことで十分に対処できます。
![]()

アフターマーケットでの売上を重視
金子 鉱山機械・建設機械ビジネスにおけるアフタ-マーケットの強みについて教えて下
さい。
古賀 自動車との比較ですが、鉱山機械・建設機械は交換部品数が自動車に比べてたく
さんあります。特に鉱山機械は 24 時間動かし、かつ長く使うことにより機械が償却され
て、使う側の利益につながっていきます。そのため部品の交換サービスは、ハードに
使って収益を上げたいと思っているお客様ほど、きちっと行う傾向があります。
また鉱山機械についていえば、業界が寡占状態であり、汎用部品が存在しません。そ
のため交換パーツなどはすべてメーカーから直接買って下さいます。しかも、部品の
点数が自動車に比べてたくさんありますから、これが大きな収益源になります。つまり
アフターマーケットは極めて重要であり、メーカー側の品質維持の努力だけでなく、実
際にサービスを行う代理店の力が非常に重要です。
私たちは、主要な鉱山のある地域は、コマツの資本が入った直営の代理店で、アフタ
ーサービスを行っていて、その価値を認めてくれるお客様が多いのも事実ですが、キ
ャタピラーは全く逆で、自社では代理店を一切経営しません。
金子 アフターマーケットをさらに拡大していくストーリーはあるのでしょうか。また、この領
域におけるキャタピラーや中国メーカーに対する優位性はいかがですか。
古賀 部品サービスと機械本体の売上比率は 50 対 50 で、鉱山機械は 50%のうち 70%
が部品サービスで、30%が機械本体です。これに対して、建設機械は 50%のうち 60%
が機械本体で、40%が部品サービスです。
もちろんこれを伸ばしたいところですが、アフターマーケットのビジネスは、製品を販売
から数年経たないと出てきません。したがって、アフターマーケットを伸ばすためには、
まず機械本体をきちんと販売する必要があります。つまり一緒に伸ばしていくのが理
想です。
「M&A+100%還元」で ROE の維持向上を目指す
金子 グローバルな開発生産体制も御社の強みのひとつだと思うのですが、トランプ関税
への対処はいかがでしょうか。
古賀 生産調達体制については 2 つの考えに基づいて実行しています。ひとつはクロスソ
ーシングといって、同じ種類の機械を世界中のいくつかの場所でつくり、その地域だけ
でなく、他の地域にも供給するというものです。例えば、ショベルカーであれば、タイで
生産したものを米国で販売する。ブルドーザーはブラジルでつくり、米国で販売する。
なぜそのような方法をとるのかというと、重複の投資を避けるためです。
建設機械の需要は地域によって増減があります。しかし、各地域においてマックス、ミ
ニマムの生産能力に合わせて投資してしまうと、過剰投資になるか、つくれなくなるか
のどちらかになってしまいます。ですから私たちは、全世界の需要を見渡して、過不足
ない全体の生産能力をもってフレキシブルに、余った生産能力を用いて、他の地域向
けに製品を製造するようにしているのです。また、海外での生産は損益に対する為替
の影響をマイルドにする効果もあります。
もうひとつの考え方はマルチソーシングといって、地政学リスクへの対応です。例えば、
中国からの部品供給が止まると全体に影響する、ということが現実にコロナの時期に
ありました。そのリスクを避けるために、ひとつの部品でも、他の異なった地域のサプ
ライヤーから供給を受けられるようにしています。
そして関税の話ですが、クロスソーシングは、トランプ関税の影響を劇的に軽減する手
段になりません。最初、中国の関税率が 145%と高く、国ごとに関税率に差があれば、
中国から他の地域に移すことによって、関税が安くなるかもなどと考えたのですが、現
在のように日本と中国の関税率の差が 15%程度だと、鋼材価格が安い中国からの調
達を止めるコストメリットはありません。そして、米国はもっと鋼材価格が高いので、中
国に 30%、50%の関税をかけられたくらいでは、中国調達の方が安いということになり
ます。ですから、クロスソーシングだけで関税に対応するのは難しいのが現状です。
金子 ROE について、キャタピラーとの差をどう考えますか。
古賀 ROE を分解すると、収益率と自己資本の違いがあるとはいえ、それだけでは全部
を説明し切れません。ROE に関しては、もう少し改善できると思いますが、どうしても限
界が生じてしまいます。
第一に、自己資本は結構高いものの、それを簡単に減らせないという現実があります。
というのも、利益が結構膨らんでいるため、100%に近い配当金と自社株買いを行って
いても、ROE を大幅に改善できないのです。
そうなると収益性を高めていくことが必要なのですが、収益性を高めるにしても、昨年
の 14%という ROE を 15%、16%へと高めるためには、毎年 100%に近い株主還元を
行ったうえで、さらに純利益を 5%くらいずつ、継続的に増やしていかなければなりませ
ん。これは非常に高いハードルです。
そこで、新しい中期経営計画では、フリー・キャッシュ・フローを 3 年で 1 兆円にして、
M&A を優先させつつも、残ったキャッシュは基本的に株主に還元すると明言しました。
M&A で売上を伸ばしつつ、100%に近い還元を行うことにより、ROE を維持向上させて
いく方針です。

\コマツさまのプレゼンと鼎談の様子はこちらからご覧いただけます/