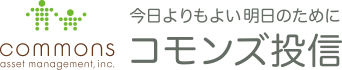ここまでのお話で、バリュー株ってなに?、グロース株ってなに?と思っていたのが、なんとなくではありますが、おおかたのイメージができたのではないでしょうか。
では、このバリュー株とグロース株が、コロナ禍、おおよそこの1年間でどういうふうに動いたのかをみてみましょう。
株式市場では市場全体の株式をバリュー株とグロース株に分けて、それぞれをバリュー指数、グロース指数として算出するスタイル指数というものがありますが、それぞれの指数のリターン推移を見ることで、市場がバリュー株に注目が集まっている局面なのか、グロース株に注目が集まっている局面なのかを把握することが出来ます。
下のグラフは、東証が算出する2020年1月を起点(=100)とした、TOPIX(東証株価指数)とバリュー指数、グロース指数のグラフ(左軸)と、バリュー指数とグロース指数の差(右軸)です。

昨年3月を安値にTOPIXもバリュー指数もグロース指数も右肩上がりです(左軸)が、TOPIXよりもグロース指数の上昇が大きく、バリュー指数の上昇はそれよりも小さかったことがわかります。
さらに、バリュー指数とグロース指数の差(右軸)をみると、昨年の11月を境に大きく変化したのがみてとれます。昨年の11月といえば、新型コロナウイルスのワクチンが開発されたタイミングです。その前まではグロース株ばかりが上がり、グロース株とバリュー株の差はマイナスに大きくなるばかりでした。それがワクチン開発をタイミングに、それまでに買われなかったバリュー株が大きく買われだして、そのマイナス差は急激に縮まり始めました。
そして米長期金利の上昇が、その動きをさらに強めました。マーケットでは、米長期金利が上昇してバリュー株が買われ、グロース株が売られたなどのマーケットコメントも多くみられるようになりました。
ここでまた一つの疑問が生まれます。金利が上がれば、株って下がるんじゃなかったっけ?です。でも、実際のマーケットでは、株価はTOPIXという指数でみる限りで上がりました。
ちょっと面倒くさい話になりますが、株式評価モデルの1つに配当割引モデルというものがあります。
株価 = 配当 /(金利 + 株式リスク・プレミアム − 成長率)です。
将来支払われる配当を現在価値に割り引いたものを株価の理論値とする、というのこの式の意味ですが、そのため、金利が上昇すると、(配当を割引く)割引率が上昇するため、配当など他の条件を一定とすれば、計算上で現在価値、すなわち株価の理論値が低下するというものです。
ということで、一般的には、金利が上がれば株が下がるという理解になります。
ただ、現在のような超低金利の環境下では、投資行動の観点から、債券投資から得られる受取利息(インカムゲイン)よりも、株式投資からの値上がり益(キャピタルゲイン)を選好する動きがまだまだ強いと思われますので、金利が上がったとしても株価は実際に上がっています。
先のモデルはあくまでも無期限の長期投資での想定で、ここから数年先をみてさらに長期金利が上がり続けるということでもないと思われるからです。
長期的に金利が上昇するには、インフレ期待が高まって実質金利が上がる、または技術革新によって経済の本質的な成長期待が高まることが必要です。
世界中でワクチン接種が終わって、人々が元の生活に戻れるとしても、アフターコロナの世界はそれまでの生活様式が変わる可能性はあるにしても、生産性の向上で潜在成長率が大きくなるとか、ひいては実質金利が上昇することはそれほど簡単に起こるわけでもないと思われます。
米長期金利が上がったといえども、1%を下回っていたものが、1%を超えて、1%台後半へと上がっただけです。新型コロナウイルスの感染拡大前に戻っただけともいえます。
そんな中、米国株をはじめ世界の株価が上昇を続けるなかTOPIXも上昇を続けました。そしてバリュー株はさらに上がり、グロース株はそれまでの上昇から調整に転じたというところが実態ではないのでしょうか。
ワクチンが開発される以前は、マーケットでは、頻繁に「K字回復」というコメントが多くみられました。
「K」という文字が右上と右下に向かう線で出来ていることから、コロナ禍で好調な業種と不調な業種の差が鮮明になっていることを表しているというものです。
ワクチンが開発される直前までは、あまりにもグロース株への投資が集中して、グロース株が超割高になる一方、バリュー株が超割安に放置されてことで、業種の差が鮮明になっていたのです。
しかし、ワクチンの開発によって、投資家は経済活動に関する最悪のシナリオを回避し、将来的に景気が幅広く回復に向かうとの期待が大きくなりました。
このことが、それまでの市場のけん引役であったグロース株からバリュー株への急激なシフトを引き起こし、バリュー株の巻き返しとなったのです。
足下では、米長期金利の上昇も落ち着いたことで、グロース株からバリュー株へのシフトも一巡し、調整を終えたグロース株が持ち直す動きもみられます。米長期金利の上昇が株式市場の物色対象に変化をもたらしたことになります。
これまでに、バリュー株の動きとグロース株の動きをみながら、コロナ禍の株式市場の動きを見てきましたが、こうやってみてくると、株式市場は、経済環境の変化と金利水準の変化で、その物色対象が変わることが見て取れます。
ただ、ここでわかることは、いつも目にするマーケットの解説は、ワクチンが開発された、金利が上がった、下がったなど、短期的な日々の変化を端的にとらえているだけで、長期的な見方ではないということです。
長期的な見方からすると、先にも申し上げた通り、バリュー株への投資は有効なはずです。また短期的には株価の上下があって惑わされることはあっても、グロース株への投資は長期的な見方をすれば将来の企業価値への収れんへの過程ともいえそうです。
そういった見方をすれば、バリュー株もグロース株も自分自身の投資目線をどの時間軸に置くかでさらに魅力的に思えてきます。
コモンズのミッションは「一人ひとりの未来を信じる力を合わせて、次の時代を共に拓く」です。時間軸は未来を見据えた長期目線です。だからこそ魅力的なのです。
コモンズには「コモンズ30ファンド」と「ザ・2020ビジョン」という2つのファンドがあります。
それぞれのファンドに特色がありますが、ここでもうお気づきの方もいらっしゃるのではないかと思います。
なんとなくではあるけれども、それぞれのファンドがバリュー株の動きと、グロース株の動きに似ているのかなと。
次回は、バリュー株とグロース株を見る際の投資指標と併せて、コモンズの2つのファンドの特色をトレーダーふっちーなりにみていきたいと思います。
では。
※記載された意見・見通し等は作成日時点のものであり、将来の株価等の動きやファンドの将来の運用成果を保証するものではありません。

トレーディング部/部長
渕上 幸男Yukio Fuchigami
国内証券会社で営業職4年。外資系証券会社に転じ委託取引や自己取引のセルサイド・トレーダーとして10年。国内投信委託会社に転じ、証券会社への売買発注にともなうバイサイド・トレーダーとして3年。その後、国内証券会社や株式投資情報会社でヘッジファンド調査や株式市場調査に従事。2015年10月にコモンズ投信に入社。
- 1
- 2