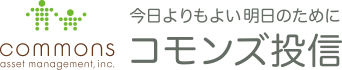かつては“斜陽産業”と呼ばれ、長らく低迷していた日本の造船業ですが、いま再び注目を集めつつあります。約20年にわたる停滞を経て、国際情勢の変化や環境問題の高まりを背景に、大きな転換点を迎えています。
(この記事を書いた人:奥 翔子 ジュニアアナリスト)
日本の造船業のこれまで
■ 国家支援による過当競争
かつて海運業と造船業は活況を呈していましたが、2008年のリーマンショックを機に、供給過剰という構造的な問題に直面しました。
その後、中国や韓国が国家の補助金を活用して価格競争を仕掛けたことで、業界全体が赤字受注に追い込まれ、日本の多くの造船所は撤退や統合を余儀なくされました。
■ 明るい兆しと残された課題
現在、約20年周期で訪れる船舶の更新期に入り、需要の回復が見られています。
しかし、日本・中国・韓国のいずれも人材不足などの影響で、かつての生産能力には至っていません。
価格の上昇は一時的な需給の影響によるものであり、技術やサービスによる差別化によって価格が形成されているわけではない、という見方もあります。
日本の持つ技術的優位性も、今や他国に並ばれ、あるいは一部では追い越されている状況です。これらの諸事情を総合的に判断すると、多くの国内造船企業の収益は、既に上限に近づいているとも考えられます。
米中対立が造船業にもたらす影響
■ 造船業の中国依存とアメリカの反応
アメリカは、世界の造船が中国に大きく依存している現状をリスクと捉えています。2024年の新造船受注の約7割が中国に集中しており、日本のシェアはわずか5%にすぎません。
近年の大型船は、運航データやエネルギー管理システムがネットワークでつながっており、万が一、中国が船を遠隔で停止するような事態が起きれば、大きな問題となります。
このような背景から、アメリカでは造船業の復活を促す大統領令が発令され、艦艇の修繕だけでも年間1兆円規模の需要が見込まれています。アメリカ政府は中国製船舶に対しては追加の入港手数料を課すことも検討されています。
■ 日本にとってのチャンス
このような状況は、日本にとって大きな機会にもなり得ます。例えば、アメリカ国内にある休眠状態の造船所を買収すれば、現地での生産能力を効率的に高めることが可能です。韓国の造船大手はすでに同様の動きを見せており、日本にとっても後れを取らないことが重要です。
また、船舶エンジンの設計分野でも、日本の技術に注目が集まる可能性があります。現在、この分野はドイツ・スイス・日本の3カ国による寡占状態にあり、特にスイスの大手企業は中国国営造船グループの傘下に入っています。そのため、独立性を保つ日本製の設計図は、他国からの信頼を得やすい状況にあります。

環境規制の強化とビジネスチャンス
■ 「環境性能=競争力」という新時代
国際的な海事機関によって、船舶の燃費規制に罰則が導入され、環境性能の高さが競争力そのものと見なされる時代が到来しました。
特に欧州では、環境性能が一定基準を満たさない船の入港を制限する動きが広がっており、環境対応の有無が直接ビジネスに影響します。
将来的には、重油に代わって、アンモニアや水素といった二酸化炭素を排出しない燃料への転換が進むと考えられています。ただし、現時点ではどの燃料が主流になるかの見通しは立っておらず、多くの船主は慎重な姿勢を崩していません。そのため、今もなお重油を使う船の発注が大半を占めています。
■ 供給と需要のバランス
現時点の発注状況は、「とりあえず必要最低限の発注をしておこう」という動きにとどまっていると推測されます。しかしそれでも需要は堅調であり、今後新しい燃料に対応した船が本格的に求められるようになれば、需給バランスがさらに逼迫する可能性もあります。
一方で、コンテナ船の空運航や一部運休も発生しており、供給過剰の兆しも見られます。ただ、燃費の悪い古い船は順次スクラップにされていくと予想されるため、中長期的にはバランスが取れると考えられます。
新たな造船施設の建設には多額の資金・時間・人材が必要であり、簡単には対応できません。このため、造船所同士の統合や買収(M&A)を通じた体制の効率化が、今後ますます重要になるでしょう。国による支援や、船主・海運会社と費用を分担する仕組みづくりも課題です。
■ 本当の差別化はどこにあるのか?
注目されがちな新燃料エンジンですが、実際にはその性能だけでは国ごとの違いは生まれにくいと考えられています。というのも、これらのエンジンはライセンスに基づいて各国で同じ設計を使って製造されており、「同じレシピで別の料理人が調理する」ような状況だからです。
本当の違いは、船の形状設計、軽量化、エネルギー管理や運航データの活用といった分野に表れます。こうした点で、日本には依然として強みがあると見られています。
■ 日本の強みをどう活かすか
日本は、鉄鉱石や穀物を運ぶ「ばら積み船」において、船体の軽さと設計の工夫により、燃費性能で高い評価を得ています。初期コストは高いものの、長期的には運航コストを抑えられるという点で優れています。
ただし、過去の激しい価格競争の影響もあり、日本の造船業界は「高くても価値がある」という強みを主張することに慎重になっているようです。現在、中国や韓国がこの分野にあまり注力していない今こそ、日本が積極的な営業戦略に転じる好機だと考えられます。

高付加価値分野への転換
■ CO2輸送船という新たな挑戦
高い付加価値を持つ船にはCO₂輸送船、砕氷船、艦艇などが挙げられます。中でもCO2輸送船は、CCUS(CO2の回収・利用・貯留)という脱炭素時代の新たなニーズに対応する、全く新しい船です。特殊な輸送タンクや冷却装置を搭載し、LNG輸送船と同等以上に技術力が必要とされます。
CCUS市場全体は、今後10年間で数兆円規模になるとも言われており、輸送インフラとしてのCO2輸送船への注目も高まっています。日本は実証船の建造で先駆けて取り組んでおり、市場成長の恩恵だけでなく大きなシェアの獲得にも期待が寄せられます。
新たな航路と市場の拡大
■ 北極海ルートという新時代の航路
北極海航路は、将来的にスエズ運河やパナマ運河を上回るほどの重要性を持つ可能性があります。地球温暖化の影響により、北極の氷が薄くなり、夏場には通行可能な期間が生まれています。この新たなルートでは、たとえば日本の横浜港からドイツのハンブルク港までの距離が、スエズ経由より約40%も短縮できるとされています。
このルートの活用が広がれば、砕氷船という特殊船の需要が高まることが予想されます。フィンランドの造船企業はこの分野に強く、日本がこの分野に進出するには、同国とのM&Aや技術提携がカギになるでしょう。
■ 船の補修市場への影響
北極海を通ることで航行距離が短くなれば、消耗部品の交換が減り、補修用部品市場には逆風となる可能性もあります。一方で、温暖化により海洋生物が活発になり、船底に付着する貝やフジツボが増えるといった新たな課題も発生しやすくなります。
氷による自己洗浄効果も減少すると考えられるため、今後は耐氷性や防汚性に優れた塗料など、メンテナンス技術の高付加価値化が進む一面があると見られます。

最後に ― 造船の未来に向けて
造船業は、建設業と同様に労働集約的で、人の手が不可欠な産業です。先端分野にはイーロン・マスクのような象徴的人物が存在しますが、造船は、スポットライトの当たらない現場の方々が技術を継承しながら、日本を支えてきました。おかげさまでいま再び世界の主戦場に立つことができます。ただ頭が下がる思いです。
保護主義の高まりやそれに伴う海運需要の減少といった懸念材料も存在しますが、皆さまの力がある限り、「地政学的な変化」と「地球温暖化」という2つの大きな追い風で時代の本命テーマになる日はそう遠くないと見ています。
【ご参考までに】
*1 日本海事新聞 2025年1月28日 「24年の新造船受注、08年以来の高水準。CGTベース、中国シェア7割超に」
https://www.jmd.co.jp/apl/article.php?no=302452
*2 コモンズ投信「ザ・2020ビジョン」2024年7月月次レポート p7 「国内クルーズ市場、新たな体験価値を提供」
https://www.commons30.jp/pdf/fund2020/2020pdf_2024_7.pdf
*3 国土交通省総合政策局海洋政策課 「北極海航路の利用動向について」 p1
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/ocean_policy/content/001476544.pdf
*4 Business Finland “Finnish Solutions for the Entire Icebreaking Value Chain” (2024年) p4
「フィンランド企業は世界の砕氷船の約80%を設計し、約60%を建造」
https://mediabank.businessfinland.fi/l/vhcQV7Lk7C-n/f/ZWv7
*5 Business Finland “Finnish Solutions for Smart Ships” (2023年) p6
「世界の大型豪華クルーズ船のうち60%がフィンランドで設計され、その3分の1はフィンランドの造船所で建造」
https://mediabank.businessfinland.fi/l/vhcQV7Lk7C-n/f/ZWv7
*6 Nature Communications (Vol.14, No.3139, 2023年) Kim, YH., Min, SK., Gillett, N.P.ほか“Observationally-constrained projections of an ice-free Arctic even under a low emission scenario.”
https://doi.org/10.1038/s41467-023-38511-8