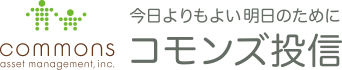去る2024年10月「第16回コモンズ社会起業家フォーラム」が開催されました。
本年度も社会課題解決のため、自ら行動を起こしたリーダー11人が、マイク1本と想いだけを手に、7分間のスピーチを行い、それぞれの熱い思いにふれることのできた貴重な機会となりました。
本記事では、フォーラムの後半で行われた、第15回コモンズSEEDCapの応援先、アクセプト・インターナショナルの永井陽右さんと渋澤健(コモンズ投信取締役会長)、馬越裕子(コモンズ投信マーケティング部/ソーシャルエンゲージメントリーダー)の三者による鼎談の模様をお伝えいたします。永井さんの受賞後の思いと、今後の展望をお聞きすることができました。
NPO法人 アクセプト・インターナショナル 代表理事
 2011年、当時大学生1年生だった永井さんは、ソマリアの深刻な状況を知り、大きな衝撃を受けました。干ばつ、飢饉、内戦が重なり、何十万もの人が亡くなっているにも関わらず、必要な支援がほとんど届いていないと知ったからです。永井さんは「日本ソマリア青年機構」を設立し、様々な障壁を越えながら、現在に至るまで活動を続けてきました。2017年、活動が世界に広がったことを契機に、アクセプト・インターナショナルと名称を変更。世界の紛争地でテロ組織や反政府武装勢力の戦闘員を受け入れ、彼らが武器を置き、新たな人生を歩めるよう支援しています。アクセプト・インターナショナルは「憎しみの連鎖をほどく」を信念とし、若者が武装勢力に加入するのを防ぐための教育や職業訓練、そして、テロ組織からの離脱を支援してきました。離脱を希望する戦闘員を保護する際には、自ら命がけで救出に向かいます。永井さんの願いは、武器を置いた若者たちが平和の担い手となること。そのために、国際規範の制定などの場にも元戦闘員たちに参加してもらい、新たな対話の場を作る。永井さんたちの前例のない挑戦は、これからも続きます。
2011年、当時大学生1年生だった永井さんは、ソマリアの深刻な状況を知り、大きな衝撃を受けました。干ばつ、飢饉、内戦が重なり、何十万もの人が亡くなっているにも関わらず、必要な支援がほとんど届いていないと知ったからです。永井さんは「日本ソマリア青年機構」を設立し、様々な障壁を越えながら、現在に至るまで活動を続けてきました。2017年、活動が世界に広がったことを契機に、アクセプト・インターナショナルと名称を変更。世界の紛争地でテロ組織や反政府武装勢力の戦闘員を受け入れ、彼らが武器を置き、新たな人生を歩めるよう支援しています。アクセプト・インターナショナルは「憎しみの連鎖をほどく」を信念とし、若者が武装勢力に加入するのを防ぐための教育や職業訓練、そして、テロ組織からの離脱を支援してきました。離脱を希望する戦闘員を保護する際には、自ら命がけで救出に向かいます。永井さんの願いは、武器を置いた若者たちが平和の担い手となること。そのために、国際規範の制定などの場にも元戦闘員たちに参加してもらい、新たな対話の場を作る。永井さんたちの前例のない挑戦は、これからも続きます。第16回社会起業家フォーラム 永井さんのスピーチはこちら↓
一人ひとりの「想い」を集め、紛争地の若者戦闘員を救い出す
~ NPO法人 アクセプト・インターナショナル永井陽右さんとの対話 ~
寄付とは、未来への投資
馬越:第15回コモンズSEEDCap受賞おめでとうございます。アクセプト・インターナショナルにとって、今回の寄付は、どんな意味があると感じておられますか。
永井:この5年、10年で、社会課題に対しての取り組みが多様化してきたと感じています。社会課題の解決もビジネスとして成立しないとサステナブルではないよねということもよく言われるようになって。僕自身も「寄付じゃなくて投資だったらいくらでもする」というようなことを言われます。「寄付は捨て金だから」と言うんですよね。でも、ビジネス的なアプローチだけでは対応できない課題は実際に存在していて、我々の活動がまさにそうです。テロや武力紛争の解決、戦っている若者たちをどうするんだっていう課題は、ハイリスクでハイコストで、リスクしかないですよね。アクセプト・インターナショナルは、半分ぐらいはご寄付で成立している。だからこそ、こんなに難しくてよくわからない仕事に真正面から向き合うことができているんです。我々は「寄付」という形でいただくお金こそが純粋に、課題解決の原資だと感じています。

渋澤:テロは、今や世界が直面しているリスクですよね。だからこそ、経済安全保障とかサブプライチェーンが必要などと言われているわけで。10年くらい前と比べてもテロがもたらす経済的な影響などを、企業もリアルにイメージできるのではないでしょうか。むしろ、長期投資の株主としては、それをイメージできないのは問題だと思います。寄付というものは実は安全保障への投資であること、捨て金じゃなくて、投資なんだという理解が企業にも可能なのではないかと思うんです。

永井:そういう理解が少しずつではあるものの広がっている気が僕もしています。そして、僕らの活動が、その前例になるんだっていう気持ちもあります。今回、コモンズの皆様が、我々のようにニッチな活動を応援してくださり、背中を押してもらえたと心から思っています。
「共感」を信じられる時代がやってきた
渋澤:今回、永井さんたちの受賞に、とても時代の変化を感じました。10年前に少年兵を救う別のプロジェクトが候補に挙がったのですが、その時は、意見が割れたんですよね。過去の選考では意見が割れるのは当たり前だったんです。なぜなら、どの人もすばらしい活動をしているから。一つに絞るのがそれだけ難しいんですよね。けれど今回は、個人投資家の声も、最終選考を行うコモンズ投信の社員の声も、満場一致で永井さんを支援することに決まった。それって、すごく珍しいことなんです。どうしてこういうことが起きたのか。別に我々は選考プロセスを変えたわけではない。ということは、社会全体が永井さんの思いに共感するように変わったということだと思うんです。その変化を受益者も社員も、それぞれの立場でキャッチしたのではないかと。
永井:ありがとうございます。とても勇気をもらえるお話ですね。数年前まで、僕自身の視野が狭かったというのもあるんですけれども「どうせ世界はわかってくれねえから」みたいな思いを持っていたんです。
馬越:その片鱗は、お付き合いしてきた中で垣間見たことがあります。
永井:本当ですか?馬越さんにも出ちゃってました?
馬越:えぇ。でも確かに最近は丸くなって、大人になられたような。永井さんは自分の言葉の中で「我々」とよくおっしゃいますけれど、それはどうしてでしょうか。
永井:設立当初「大人は口だけだ」「大人は敵だ」みたいな気持ちがどこかにあって。でも、自分が大人になって、ここ3年ぐらいですかね、今のやり方じゃ全然ダメだなと。自分も口だけになりうるのではないかというのが見えてきたんです。 NPO化したときは少数精鋭、紛争地の最前線にいるような最強の部隊を作ろうとしていたんですけれど、最近は、もっとその最上流、いろんな人をどう巻き込んで「我々」として戦えるか。「我々」をどう広げられるかが大事だと思うようになって。「我々」の中にいるのは、もちろん当事者たちです。今戦ってる若者たち、武器を置いた若者たち、みんなで徒党を組んで「我々」としてニューヨークやジュネーブで戦いたい。大人に勝つにはそれしか勝ち目がないんですよね。大人、手ごわいですから(笑)。それから、これまで本当に多くのご寄付、ご支援をいただいて、それがなかったら、我々はほんとに存在してない。だから、関わってくださったすべての人を含めて「我々」だなって思っています。
当事者とともに言葉を創り、伝えていく
永井:最初は「日本ソマリア青年機構」っていう名前だったんですが、ソマリアだけではなくてあくまでも世界のテロと武力紛争の解決に挑まなければと考えましたし、何より自分も年を重ねてもう青年じゃなくなるぞっていうのもあって、改称しようと思いました。それで、我々の活動の姿勢はなんだろうと考えたときに「受け止める」というイメージが浮かんだんです。英単語の辞書を引いて“accept”を見つけて。すごくいい言葉だと思いました。
渋澤:「コモンズ30ファンド」の30は、投資に30年目線を持ちましょうということなんですが30年後の永井さんは、たぶん今の僕の年齢に近くなっている。ちょっと白髪も出てきたり、お腹も出たりしているかもしれない。そのときのアクセプト・インターナショルが達成していたい目標はありますか。
永井:30年後ですか。やっぱり、テロや武力紛争が少しでもない世界にしていなきゃという気持ちはありますよね。でも、もう少し近くを見ると、2031年までにテロや武力紛争に関わる若者の権利とエンパワメントを保障する国際法規範を作ると決めています。その母体としてグローバルな「タスクフォース」を作りました。一般的によく使われる「キャンペーン」みたいな言葉ではなく「タスクフォース」としたのは「どこかの世代で達成できていたらいい」じゃなく「我々がやる仕事(タスク)なんだ」という気持ちが強いからです。

渋澤:その国際法規範ができた未来は、どういう社会になっていてほしいですか。
永井:国際法規範を作ろうとしているのは、今戦っている若者たちに国際法規という言葉がないからです。彼らには言葉が必要なんです。子ども兵にはそうした言葉が多数あるから色々と打ち手がある。しかしボリュームゾーンである若者の戦闘員たちに対しては存在していないのです。今までは「我々だけの言葉」だったので、それを、ほんとに「みんなの言葉」にしていかなきゃいけない。そして、ほかでもない、ここ日本からやっていきたい。
馬越:永井さんは、日本にそのポテンシャル、パワーがあると信じているんですね。
永井:そうなんです。日本にはその力がある。例えば、ハマスの若手リーダーと話していて言われました。「キリスト教でもない。イスラム教でもない。もちろんユダヤ教でもない。そんなお前、おもしろいね」って。日本が持つユニークさは、国際平和とか国際紛争解決にまだまだ貢献できる。でも今までは生かし切れていなかったんですよね。だったら俺がやると。前例はないけど、そんなのどうだっていい。国際法規範という新たな言葉を持ってして、取り残されてきた多くの人々にそれを伝えて、新たな価値をみんなで作る。これから我々がやるべきことはそれに尽きます。
コモンズSEEDCapとは?
「コモンズSEEDCap」は、コモンズ投信が2007年の創業から取り組んできた寄付プログラムです。その最大の特徴は、投資信託の運用収益の一部を原資として、社会課題に挑むリーダーたちに寄付を行っているということです。この仕組みは、投資を通じて未来を築くというコモンズ投信の理念を具現化したものと言えます。応援先の選定には、個人投資家をはじめとするコモンズの「お仲間」の声を反映する仕組みがあり、透明性と共感を大切にして運営してきました。未来を担う社会起業家の活動を、資金面だけでなく、広報やネットワークづくりなど多方面からサポートしています。今年、設立15周年を記念し、これまでの取り組みをまとめた「寄付インパクトレポート」を発行しています。
ご興味のある方は、こちらよりダウンロードできますので、ぜひご覧ください。
「SEEDCap 15周年記念 寄付インパクトレポート」
https://www.commons30.jp/pdf/donation/seedcapreport.pdf